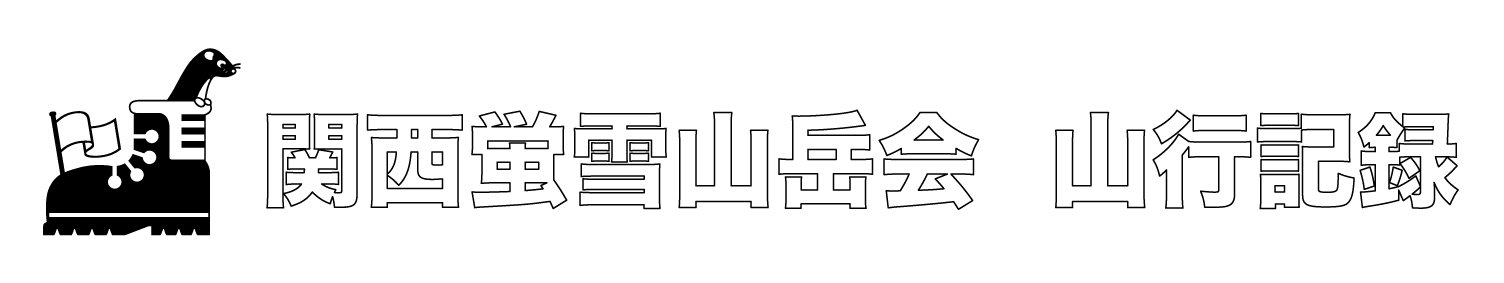日時: 1994年5月21日
メンバー: 美甘、柴谷、秋田、中尾、他会1名
天気: 晴時々曇
深夜、片貝川上流にある無人の片貝山荘に迄入る。水道栓は締まっているが、電気は使えるので非常に助かる。
起きて外を見ると、大勢の人が上がって来る。昨夜は1台も無かった車も20台近くに増えている。その殆どはどうやら山菜採りに来ている様だ。例年は林道の終点まで車が入れるらしいのだが、今年は林道の一部にまだ雪渓が残っており、片貝山荘より板を担いで歩く事となった。右手の宋次郎谷を過ぎ、約1時間程残雪を背景にした新緑の美しい阿部木谷渓流沿いの林道を歩くと、大きな堰堤にぶつかる。ここから谷は大きく右に曲がっており、通常はここ迄車が入れるとの事。この取り付き点の標高は994m、そして毛勝山の標高は 2,414.4m。標高差1,420mの長い登りのスタートである。
堰堤の上に上がるとそこから先の谷は一面雪渓で覆われていた。年によってはこの季節既に雪渓が割れてシュルンドが開いている事もあるらしく、その場合は板を担いで側壁をへつる事になりそうだ。今年はその心配も無いので、皆スキー板を引きずって行く事にする。300m程進むと谷は少し左に曲がり、前方の視界が開けて来る。目の前には毛勝谷と大明神谷との二股があり、谷幅は広く、朝日の当たった雪渓がとても眩しい。
1,400m付近迄登るとそこから毛勝谷は一直線となり、奥の二股から先は突然その傾斜を強めている。ここから稜線に出る迄の標高差 900mが最も厳しい登りである。久しぶりに登るというK氏は既にバテバテで、蛍雪4名が先行する。さらに珍しく中尾の姉さんが少し遅れ出す。何で私が柴谷さんに付いて行けないの等と言われると複雑な心境である。
最後の40度近い斜面を登りきると、稜線に飛び出す。ウオーと思わず叫びたくなる景色である。右手には猫又山、赤谷山から剣岳につながる北方稜線が、そして深い谷を挟んだ対面には針ノ木、爺、鹿島槍、五竜、唐松、白馬三山、雪倉、朝日と続く後立山連峰が、一つの視野に入ってくるのである。ここから稜線をほんの少し登ると毛勝山の山頂に着く。毛勝山の北側にはサンナビキ山が連なっており、最近は忘れかけていたが「こんな所に厳冬期に入れるだけの力が有ったらなあ」と言う想いが心の底から湧いて来る。
非常に遅れてしまったK氏を待つ事2時間。いよいよ滑降の開始である。出だしは40度近い斜面なのだが、谷幅は10~20mある上、雪質はちょうど良いザラメ雪に変わっており、実に快適にスキーのテールが回ってくれる。急傾斜の900mの高度差を一気に滑り降りる。別の数パーティーにはスキーを担いだものは居らず、急斜面をエッサホッサと下りている横に新しいシュプールを描いて滑るのは実に心地良いものである。この間わずか15分位だろうか、いつも思うのだが何故わずかな快感の為に幾時間も板を担いで登るのだろうかと。
大明神谷との出合まで下りて来ると、雪渓の上は一面枯葉や小石で埋め尽くされており、スキーの板の裏を傷つけぬ様に必死になってちょこまかとターンを繰り返す。それでも無理矢理取付きの堰堤までスキーを着けたままで下りてくる事が出来た。
今宵の酒の肴にと山菜を採りながら片貝山荘に戻り、夕方富山に用事のあると言う美甘氏に買出しを頼む。その夜は新鮮な海の幸と取れ立ての山菜を肴に久し振りに夜遅く迄騒いだのだが、姉さん方は2人共にヘベレケになって管を巻いていた。
[タイム] 片貝山荘(7:40) 取付(9:00) 毛勝山(13:00-15:00) 取付(15:50) 片貝山荘(17:00)