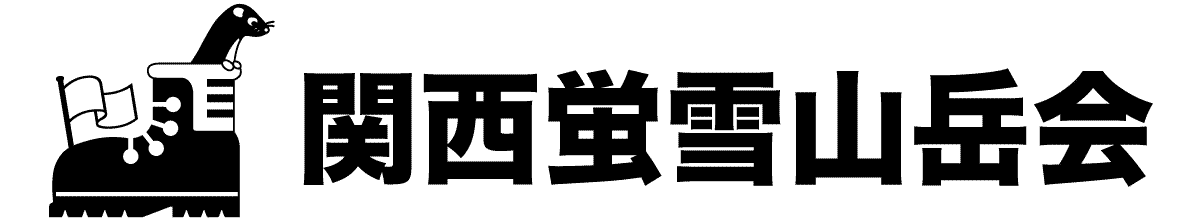日程: 2018年11月3日(土)~4日(日)
メンバー: 松並、他10名
8:10宇奈月温泉~9:30欅平駅10:00~12:00志合谷~12:20大太鼓~13:10折尾谷~14:40阿曽原温泉
3日朝6時に立山駅前に集合する。室堂、弥陀ヶ原の紅葉のピークも過ぎたためか休日でもまだ人はまばら、駐車場にも余裕がある。車に乗り合わせて立山ICから黒部へ出発、道中の北陸道からは薬師~立山~剱~毛勝の山並みがくっきりと見え、すっきりとした秋晴れが少なかった今秋、剱の頂が平野から見えるのは久しぶりと聞く。2日間の好天を期待させてくれる。宇奈月のトロッコ電車駅に着くと大勢の人が始発のトロッコを待っており、紅葉ハイカーにまぎれながら2番目のトロッコに乗る。8月のお盆に清水尾根をおりて祖母谷温泉に泊まった時以来、今年2度目のトロッコ、80分の乗車時間もワイワイおしゃべりであっという間に欅平に到着。朝一の空気はひんやりしていたが、陽射しが暖かく、一日の行程の注意点を確認してからいよいよ下の廊下へ出発。紅葉はまさに見頃で、黄色・赤の鮮やかな森、周囲の山の上部には雪も被り、青空との白、赤、黄のコントラストが美しい。水平歩道の入り口までは直登の急傾斜だが、涼しい秋の風に助けられ、あっという間に到着。足元が水平になると一気に高度を上げた事に気付き、はるか下の黒部の流れを見ると怖いが、番線があり、足元が十分整備されているため安心感がある。対岸には奥鐘山の大岩壁、昔黒部の河床で温泉を掘ったりスイカを冷やしたりしながら奥鐘の岩壁に登ったとの話を聴きながら、志合谷を目指す。志合谷のトンネル内はどの位の水位なのか、冷たいだろうなあと考えながら歩いていると阿曽原を出た登山者とすれ違うので、すれ違いのたびに水位を聞くと足首ほども無いという。トンネル手前でヘッドランプを点けて歩き始めはほとんど水が無い、濡れずに済むかなと思っていたら出口に近づくほど水位が上がり、足を置く場所を考えてもやっぱり足首まで浸かってしまった。志合谷を過ぎるといよいよ大太鼓へと続く、水平歩道の名前の由来と道を付けた歴史を感じる道になる。谷に入るたびに見える谷の向こう側の道は本当に一直線に、断崖に一筋の筋となって伸びている。谷を過ぎて振り返れば、やっぱり一筋の筋となっていて、岩盤はコの字にくり貫かれ、足元に木材を通して道にしている箇所も何か所も続く、気を抜けない場所が多いが足を止めれば鮮やかな紅葉と黒部の流れに癒された。5時間弱の行程で最後に阿曽原の小屋が見えてからの最後の下りが長く感じたが、阿曽原に到着、小屋に挨拶すると、今日は人が多いからと温泉に1時間の女子タイムを作ってくれた。5人の女子メンバーでのんびりと浸かった阿曽原のお湯は少し熱かったけれど、黒部の対岸の紅葉を眺めながら温泉に入れる山の温泉は心も体も癒されて明日一日も元気に歩ける気がした。熱い阿曽原の湯に浸かりながら、少し前に読んだ吉村昭の高熱隧道を思い出す。志合谷、折尾谷、阿曽原谷、仙人谷は黒部開発の黎明期の舞台、高温の岩盤にダイナマイトの自然発火、泡雪崩と怖い話ばかりだったが、今その場所にいると思うとなんだか不思議な感じがした。
5:00阿曽原温泉~6:00仙人谷ダム~6:20東谷吊橋~8:00十字峡~9:30白竜峡~10:00黒部別山沢~12:00内蔵助出合12:30~13:50黒部ダム
ヘッドランプを点けて阿曽原を出発するが、仙人ダムに着くころには明るくなってくる。空には少し雲があるが、今日も天気は良さそうだ。東谷吊橋からいよいよ旧日電歩道となり、一気に高度感が増してくる。番線がしっかりついているが、昨日よりもさらに黒部の水面が低く感じられ、足元も狭くなっている。周りの景色を見るとき、写真を撮るときは止まってというルールを守り、峡谷の景色を楽しむとあっという間にS字峡に到着した。何度も写真では見てきたが、黒部の青白い流れと流れを囲む岩壁、岩を彩る紅葉は、澄んだ空気と黒部の流れの音と相まってまさに絶景。十字峡への道も昨日に増して怖かったが、ずっと続く紅葉の絶景にまったく飽きる事が無かった。十字峡広場では小腹を満たしつつ、荷物を下して十字峡を見に川岸に降りてみる。十字峡は剱からの剱沢と爺ヶ岳からの棒小屋沢が同じ場所で黒部に交わる場所。長く広い黒部の流れの中で、十字峡の流れに自然の不思議を感じた。十字峡から上部はより足場が不安定になる。幾つものハシゴや斜面に組まれた足場を通過するごとに、毎年この道を整備する人の大変さが身に染みてくると同時に、阿曽原で聞いたこのルートを逆コースだが4泊5日で歩ききった人の話を思い出す。その人は外国の方で、なんと道幅の1.5倍の巨漢だったそうだ。ふつうの人が歩いてもスレスレの道をどう歩いていたのかと想像するとなんだか可笑しくなってくる。高度を少しずつ下げ、黒部の流れに近づいてくると白竜峡となる。渦巻く黒部の流れがはっきりと見え、とにかく流れの音がすごい、迫ってくる大迫力の音と川幅が10mもない峡谷を流れる水の迫力に、押されるような黒部の自然の力を感じた。上流の黒部ダムから放水をしており、水量が多かったようだが、大迫力の音はずっと耳に残っていた。白竜峡から先も標高が1000m程度である事から紅葉を楽しむ事ができ、大タテガビン沢付近の紅葉、新越沢・鳴沢小沢・鳴沢など時々現れる対岸の小滝に飽きることなくあっという間に内蔵助谷出合に到着した。内蔵助出合まで7時間程、黒部ダムまでは2時間かからないため大休止をする。十字峡からゆっくり休めるところはほとんどなかったため、ゆっくりと昼食、丸山東壁を眺めながら昔のクライミングの話を聴いたり、内蔵助谷の先にある内蔵助平やハシゴ谷乗越に行きたいと来シーズンの計画を立てたり、休憩中も楽しかった。内蔵助出合を出発すると黒部の河床も少しずつ広くなり、終点の黒部ダムに近づいてくる。早く黒部ダムを下から眺めてみたいのはあるが、ダムが見えたらこの下の廊下の旅も終わりに近づいていると思うとなんだか寂しくなってくる。いよいよダムが見えるところに着くと、観光放水のシーズンは終わっていたが、放水中で、対岸に渡る橋もすぐ下に流れがあり、ダムからの風で涼しかった。ダムまでの急登を一気に上がるといよいよ黒部ダムサイト、14時前に無事到着したことにほっとして、2日間歩ききった満足感と疲労感でいっぱいだった。黒部ダムからのケーブルカー、ロープウェー、トローリーバスは初めてでウキウキしていたが、さすがにダムから立山駅は長くて最後の室堂からの高原バスは寝てしまった。充実の2日間で、また訪れてみたい黒部下の廊下だった。
黒部川 下の廊下